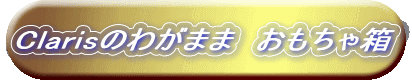
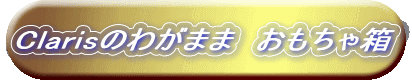
|
大容量のハードディスクを使用する場合、幾つかの仕様や特徴があります。 この仕様・特徴を理解することにより、マルチブート環境をスムーズに作成する必要があります。 ここでは、これらの内容について記述します。 IDEインターフェースのハードディスク(以下、IDEハードディスク)のうち容量の大きなものに、Linuxをインストールできない等のトラブルが発生する事があります。 このような問題から、Linuxを敬遠する人も少なくないと思います。 ですが、正しく仕様・特徴を理解することにより、問題なくマルチブート環境・Linuxのインストールをすることが出来ます。 通常ハードディスクに、アクセスする際は内容を読み書きする位置を特定するために、シリンダ・ヘッド・セクタのパラメータを利用することになります。 IDEインターフェースでは、シリンダを16ビット、ヘッドを4ビット、セクターを8ビットで指定します。 この事から、ハードディスクの最大容量は、 最大値 = 2^16 × 2^4 × (2^8 -1 ) × 512bye = 約137Gbyte と成ります。 しかし、実際には、様々な制約があるため、少ない容量のIDEハードディスクしか使えない場合があります。 ハードディスクやハードウェアの制約によっては、使用できるサイズは528Mbyte制約や8.4Gbyte制約等があります。 これらは、インターフェースの制約に縛られます。 528Mbyte制約イメージ図 8.4Gbyte制約イメージ図 これらの制約は、インタフェースもしくは、ハードディスクの設定値の小さいほうに合わされられます。 ですが、インターフェースとハードディスクそれぞれが同一の設定値を採用することによりハードディスクの最大サイズを使い切ることが出来ます。 この仕様が拡張INT13(IDE仕様の上限)と言うインターフェースです。 ただし、インターフェースの拡張により ・BIOSが拡張INT13に対応している ・ディスクを直接アクセスするO/Sやソフトウェア (ブートローダー等)が拡張INT13に対応している と、言う条件を満たしている必要があります。 満たしていない場合は、8.4Gbyteまでの使用となります。 現在ご使用のPC・マザーボード・ハードディスクがそれぞれどの仕様で定義されているかは、マニュアル・取り扱い説明書等を参照してください。 厳密には、上記以外の制約を受けいます。 |
|||||||||||||||||||||